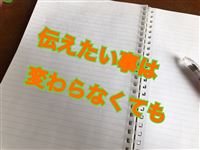
2019.05.30
五月とは思えない程の暑さがあり、梅雨入り前という事をうっかり忘れてしまいそうな日が続いたかと思えば、今朝は寒くて、着るものの出し入れが忙しいです。
いつもご覧頂きまして、有難う御座います。
小諸市のくろとりピアノ教室です。
東京・表参道でのピアノ導入法セミナーが、今年度も始まり、受講して参りました。
昭和から平成、平成から令和へと時代が変わるにつれて、ピアノ教育も大きく変わって来ています。
私がピアノを習い始めた昭和の指導の仕方と、私がピアノ教師になった平成とでは、変化がありましたし、これからの令和でもまた、方法は変わっていくことでしょう。
昭和は、根性とか努力をテーマとしたアニメやドラマが多くあり、それを見て育った私達は、何かを得ようとした時に努力をする事は当然と思って育ってきました。
練習が好きではなくても、アニメなどの主人公が頑張って練習しているのだから、そういうものなのだと思い、実際私は、毎日ピアノの練習をしてきました。
しかし、昭和の根性論・考え方が、徐々に薄れてきつつあり、教室に通いさえすれば、半年でピアノが弾けるようになると勘違いされているケースもあるようです。
子供時代の、努力が必須なピアノという習い事を通して、投げ出さない力、根気強さ、粘り強さが育ち、それこそが将来、勉強、受験、社会に出た時に底力となって活かされるのだと思います。
今回の講座では、ピアノ指導で伝えたいことは変わらなくても、指導の仕方は変わっているし、変えていかなければならないという事や、指導には順序があるという事を学びました。
この講座は、表参道で開かれるようになって10年になるそうですが、受講生には、くろとりピアノ教室でも採り入れている「ミュージックキーピアノ指導システム」で育ったかたが、ピアノ教師となって学びにいらしていたり、遠くは三重県からお見えになっていたり、現役のピアニストの方もいらしたりと、様々です。
そこから考えても、この指導システムの歴史の長さと、遠方からでも、ピアニストさんでも受講したいと思わせる程、ピアノ関係者に支持されていることを感じます。
ピアニストさんは、「この講座だけは、欠かせませんよ。」と仰っていました。
講座以外の時間にですが、このシステムの教材が、どんな風に、どんな想いで作られたかというお話をお聞きしました。
まだ真っ新で、本当に指導が難しい導入期の子供たちに、如何にして解るように伝えていくかを、指導の現場に立ちながら、議論に議論を重ねて生み出されたものであることをお話下さいました。
くろとりピアノ教室では、6年前からこの指導システムを採用していますが、教材が誕生する際の熱い想いが沢山詰まっているからこそ、レッスンでより良いものをお伝え出来るようになりました。
私は、こちらの講座以外に、「ピアノ教本全般の歴史」や、「譜読み指導研究」や、「リズムやドレミのシークエンス(順番)」などの講座でも学んでいるのですが、その所々に、くろとりピアノ教室で採り入れている指導システム内容が登場するのです。
それは、当教室の方向性が間違っていないことを示すものとして、本当に嬉しく思っています。