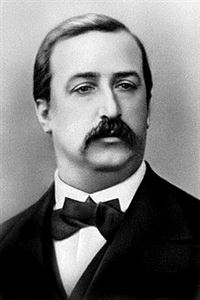
2024.09.30
《ダッタン人の踊り》は生徒さんに人気がある曲のひとつです。
ピアノのテキストでは抒情的な部分の一部をアレンジしてある短い曲ですが、そのほんのさわりだけ弾いてもこの曲の魅力が香り立ちます。子どもさんはリズムのある楽しい曲はもちろん好きですが、こんなメランコリックな曲も心に受け止めてくれます。
《ダッタン人の踊り》はボロディン作曲の【イーゴリ公】というオペラの中の曲。ダッタンとはモンゴルという意味です。祖国のために戦い敵国の捕虜となってしまったイーゴリ公ですが、その勇敢さに敵の王が敬意を払い宴席が設けられます。そのシーンでこの曲が流れ、合唱と共に人々が踊ります。
前半は管楽器が美しい世界へ聴き手をいざないます。フルート、オーボエ、クラリネット、イングリッシュホルンなどが交代で現れて奏でる、悲しげでちょっと懐かしい繊細なメロディーは、つい口ずさんでしまいます。後半はティンパニの音が身体を突き抜けリズムがはじける大地の踊り。心にも身体にもダイレクトに訴えかけてくる音楽が、広がる大平原の美しさや、自然の中で生きる生命の原点、古代からの命の躍動を感じさせます。
ボロディンはフランツ・リストとも交流がありました。初演に失敗した《交響曲第2番ロ短調》を70歳のリストがドイツ初演をプロデュースしてボロディンの名を広めたり、後年再会した折にも、ボロディンのピアノ曲《小組曲》と《スケルツォ》をリストが気に入って弾いたりしたといいます。
そのピアノ曲は民族調でありながら、洗練された親しみやすい曲調です。《小組曲》は7曲から成る小品。《スケルツォ》は小気味よい軽快な曲。なるほどリストも喜んだというくらい、弾いてみたいと思わせる魅力があります。
彼の作品の素晴らしさは、ドビュッシーやラヴェルといったフランスの作曲家にも影響を与えました。ラヴェルは《ボロディン風に》という美しい曲を書いています。
さてボロディンは私達音楽家内では作曲家として認識されていますが、本業は化学者と医者でした。よって化学者仲間内ではその分野の偉業を成し遂げた化学者としてのみ認識されているのだとか。(音楽家だと知らない人もいる?)余暇の時間を作曲にあてていた、と言いますから日曜大工ならぬ日曜作曲家と呼ばれることもありますが、どちらもものすごい才能、二刀流です。
さて。
つい先日まではボサノバでご機嫌にアイスティーを飲んでいたわたくしですが、朝晩の風のにおいが変わって少しずつ秋が近づいてくると、なんだか急にさびしくなって《ダッタン人の踊り》を聴いて温かいコーヒーをすする今日この頃です。
熊本市
東区健軍ハートピアノ教室