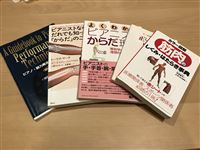
2025.09.20
ご訪問ありがとうございます。
最近はアクセスが増えてきました。
長文ですが、お読みいただきありがとうございます。
私は頭の中が、常に思考し続けるタイプですので、時折アウトプットして整理しています。
なので、書こうと思えばいくらでも書けます。
あまりに考え続けてしまうので、本でも読もうかなと思っています。
愛読書は、文芸作品か、論文ですが、、
何か物事に取り組むときは、情報を集めて、見よう見真似でやることはないタイプです。
情報は大事ですが、そこに信憑性があるか、論理的な裏付けがあるか検証します。
物事を決める時は、自分の頭の中の知識のデータベースと照らし合わせます。
そして、瞬時の直感で決断します。
自分のことですからね、人に相談することはまずないです。
自分の直感が1番正しかったと思うので。
なので、普通とは違う独自の視点や取り組み方が出来るんだと思います。
インベンション2曲、ハイドンのソナタ、近現代を練習している小6生徒さん。
身体が大きくなると、タッチや奏法を見直す必要が出てきます。
まだ手が小さい頃は、音量を出すために腕の重さを利用して、打鍵していました。
よく子供が腕や身体を揺らして弾くのは、そのためです。
注意をしても、音を鳴らすために無意識に揺れてしまうことがあります。
ロマンはそれでいいのですが、バロックや古典は、音の粒が均等に揃っていた方が綺麗なので、腕を揺らさずに指先で弾いた方がいいです。
レッスンで根気よく指導したら、気がついたようで、昨日はとても良くなっていました。
私は街のぎく普通の教師ですが、ピアニスト活動をされていた先生にレッスンを受ける機会に恵まれました。
時に国際的なピアニストのレッスンを受ける機会もありました。
自分がそれが出来たかはともかく、その教えを論理的に分析して、今のレッスンに役立てています。
解剖学の本や図鑑も、昔から眺めるのが好きでした。
ピアノの構造、鍵盤のアクション、ハンマー弦、ダンパーの仕組みを分解して考えるのも好きです。
人の骨と関節と鍵盤のアクションの関係性で、音色が作られる。
人の骨は筋肉で繋がり、その筋肉は神経回路を通して脳が動かす。
タッチの指導は、偉大な先生に授けて頂いた感覚と、解剖学、脳科学、ピアノの機会工学の知識に基づいています。
暗記するほど読み込んだ書籍を、また眺めていこ。
そして、生徒さん方にも論理的に説明していこうと思います。