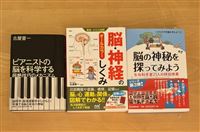
2025.01.23
トピックスをお読みいただきありがとうございます。
医学科5年生の娘は今週、大学病院で脳神経内科の実習中です。
指導して頂いている先生は理Ⅲを卒業後、ハーバード大学で研究された日本の脳神経内科トップの方です。
脳神経内科はおそらく医学でも最も難しく、医師の中でも最も頭の良い方達と認識されています。
病院で患者さまの診察をしながら知識を勉強するのですが、午前に一周しただけで頭使いすぎてヘロヘロになったそうです。
そして、午後は教授がハーバードで発表した論文の勉強会。難しい英語の論文を、その場で6人で順繰りに当てられて、皆さんの前で和訳。それが3時間休憩なしの通しで授業。
大学受験でハードに英語を勉強しておいて良かったと心から思ったそうです。
頭がヘロヘロになって帰宅しましたが、深夜に練習して、今朝も5時に起きて練習してから学校に行きました。
医大生はそのくらいタフじゃないとやっていけないんですよ。
脳神経内科には行かないけれど、教授は大好きで研修先の病院の推薦状は先生にお願いしたいそうです。
脳科学は本当に難しいですよね。
私も脳科学の本は時々読み返します。
脳は科学は身体の解剖学とは違い、解明されていないことが多くて謎に満ちてるんですよ。
ピアノのレッスンには、解剖学と運動力学の知識が必要ですね。
お子さんの場合はそこに、発達心理学の知識が不可欠です。
大人の場合は脳科学の知識が必要ですよ。
生徒さまを、解剖学を元にボディーマッピングをして、運動力学の知識で奏法を見させて頂いて、その認知の状況を脳科学の観点で判断して、言語化して的確なアドバイスを差し上げる。
大人ピアノのレッスンはこのように、私の頭の中を駆け巡ります。
ピアノが独学では出来ない理由は、俯瞰してメタ認知が出来るには相当な経験が必要で、それはプロのピアニストでも難しいからです。
弾けない理由など、客観的に誰かに見てもらわないと分からないんですよ。
その人の無意識下に入っている、データの内容や量、引き出せるスピードを瞬時に判断して言語下して伝える。
それが私のレッスンです。