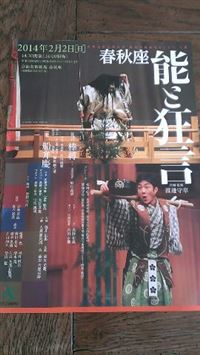
2014.02.11
狂言「棒縛」シテの太郎冠者は野村萬斎さん。
「これは このあたりに住まい致す者でござる」と、狂言おきまりの始まりの台詞。
主人がこれからお出かけ予定、心配事が…実は、主人の留守中、家来の太郎冠者(男A)と次郎冠者(男B)が、鬼の居ぬ間にいつも酒盛りをしていたのです。
そこで、次郎冠者を呼び出し、太郎冠者を縛り上げる相談をする。近頃、棒術の稽古をしている太郎冠者に棒の型をさせ縛ってしまえと、次郎冠者。はたして二人の計画通り太郎冠者は長い棒に手を広げたまま縛られてしまいます。そんなこんなで結局次郎冠者も縛られる。安心した主人はでかけていくのです。
その後、しばられたままの不自由な二人が、やっぱり酒を盗み、飲めや歌えや踊れやのクライマックスを迎える。ここが面白いのですが、主人が帰ってきてからがまたまた笑えるのです。爆笑の中退場。
休憩でクールダウンの後は、能「船弁慶」
誰もいない何もない夜更けのように静まり返った舞台に、「お調べ」が聞こえてきます。静けさと緊張感が高まったところに遠くからお囃子の音が流れてきたら、能の始まりです。勿論拍手などはなく、静かに始まります。
前場、後場の二部構成。
前場、兄の源頼朝と仲たがいをした源義経は、鎌倉方から逃れるために西国へ向かう道中。同行していた恋人の静御前(前シテ)に都に帰るように諭す。それを悲しみ、静は別れの舞を踊ります。
後場、静と別れた義経と武蔵坊弁慶は出航する。(この時の船頭が間狂言で野村万作さん)海に出ると、急に荒れはじめ、波間からは滅亡した平家一門の平知盛の亡霊(後シテ、実は前シテと同じ人)が現れる。必死で船をあやつる船頭。長刀をふりかざす亡霊に数珠をもんで祈祷する弁慶。冷静に立ち向かう義経の様子を描く。
たった4人の囃子方と地謡の8人だけのBGM。スローモーションのような役者の動き。しかも子方の義経は全く動かずたったまま。力強いが1秒1字くらいのスピードの台詞。にもかかわらず、荒れ狂った海の動きと亡霊の執念、弁慶の果敢な戦いが、すごい迫力を感じます。
この劇場は、歌舞伎仕様なので、能楽堂にある橋掛かりの代わりに花道を使っているのですが、シテは視界の狭い面を付けて、手すりもない長い花道を亡霊が走るのです。超スペクタクルファンタジーでした。にもかかわらず、最後は拍手も控えめのパラパラパラ…静かに終了です。
豊田市の中学生は能楽鑑賞体験教室という授業があり、豊田市の誇る能楽堂に皆授業を受けに行くのです。中学生が能楽堂に行くなんてすごいですねぇ~わからない世界ではなく、わかる世界にするのが教育ですよね。