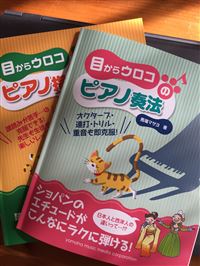
2016.10.24
今日は朝から秋晴れの静岡市です。
朝から11月のお便りの仕上げをして、今印刷中です。
今月のピアノ講師ラボの音声教材、今月は馬場マサヨ先生の「ピアノ奏法」について。
CDの音声教材なので、毎月車を運転しながら、お勉強しているのですが、今回はピアノを弾くときの筋肉や骨についての説明が多数。
いかに自然な状態でピアノを弾くか…。ということにとっても興味あり。
でも、骨の名前や筋肉の名前、「伸筋」や「屈筋」などが出てきて、運転しながらどこの骨??どこの筋肉??と想像が難しかったので、馬場先生の本を購入してきました。
本を読んでいると、音声教材の内容が思い出されス~と頭に入ってきます。
馬場先生も指の使い方や動かし方が違い無理な奏法をしていたので、演奏会前は針治療に通ったり、腰を痛めて若いころにぎっくり腰を何回もやられたりと苦労したそうです。
でも、現在は痛いところもなく、楽にピアノを弾けるようになったそうです。
私も音域が広かったり、たくさんの和音を同時に弾くような曲だと、腕を痛めることもありました。
練習して痛めては、整骨院にかかり治療(>_<)
そして、今も両腕の前腕が痛い…(悲)
なぜだろう…。いつも弾かないラテン系の曲を練習して余分な力が抜けきらないのかなぁ…と感じていた時のドンピシャの内容でした。
まず、タイトルにもした日本人と西洋人の違いが関係しているとのこと。
私たちは全身、伸筋と屈筋を使って動いていますが、西洋人は日常的において、伸筋をよく使っているそうです。
日本人は主に屈筋を使って生活しているようです。
これはピアノ奏法においても同じことのようです。
オペラやミュージカルの歌手が思いを込めて歌う時は「上体は上向き」で、腕は「ひじを伸ばす」ように歌う。→伸筋活用
でも、演歌など日本人の多くは思いを込めたり、力を入れるときは「上体を曲げ」、「ひじを内側に曲げ」て歌う。→屈筋活用
なるほど!!言われてみるとその通り。
その他、ノコギリの使い方も西洋のノコギリは押し出すときに、切れていくそうです。
日本で使っているのこぎりは引くときに切れますよね。
面白い違い(^^♪
こんな日常の筋肉の使い方もピアノに関係しているんですね。
疲れない、腕を痛めない奏法が身につくように、まず自分で試してみたいと思います。